こんにちは!
経済的自由を日々妄想するアラフォー夫婦です。
本日のテーマは、我が家のマイホーム購入記です。
内容が長いので、2回に分けてお送りします。
今から9年前の話になるので、相場が高騰している現在とは環境が異なりますが、
少しでも参考になりましたら、幸いです。
1 我が家の住居費について
マイホーム購入で重要になるのは、なんといっても支出(返済額)ですよね。
そこでまずは、我が家の住居費の推移を整理してみます。
我が家の家計管理の記事でも書きましたが、結婚した当初は賃貸住まいでした。
住居費の推移を整理すると、以下のようになります。
1年目は、妻側の一人暮らし1DK賃貸に夫が潜り込み、家賃は7.5万円
2年目は、リノベ2DKに引っ越し、家賃は12.3万円
その後、現在のマンション区分を購入し、ローン返済と管理費等を合わせ、月18.5万円
なお、住宅ローン減税を活用しているため、昨年は年間で40万円が戻ってきました。
なので、実質的な支出は、月18.5万円-3.3万円=15.2万円ほどでしょうか。
なお、金利と持ち分は「夫:3.7 固定、妻:2 変動」で組みました。
今後、金利は上昇していくと思いますが、妻の残債は1500万ほどなので、
金利上昇の影響は、それほど大きくないかなと楽観視しています。
2 マイホームを購入した理由
ちまたでは、賃貸 VS 持家 の論争がありますが、
それぞれ、ライフスタイルに応じてメリット・デメリットがあると思います。
投資だけの目線で言えば、賃貸の方が有利なのかもしれません。
例えば、DINKSのステージ、子供のいるステージ、老後のステージ、それぞれに合わせた最適な広さで、最適な賃貸相場で暮らしを変化させ、余剰資金を投資に回すといった考え方がありますね。
ですが、私たちの性格上、ライフステージに合わせて賃貸暮らしを変化させ、
なおかつ、投資についても考えるといった生活は、精神的に忙しくなるかなと考えました。
マイホームは一度買ってしまえば、住居費はほぼ固定なので、将来のマネープランの見通しが立てやすいというメリットもありますね。
また、仕事や子育てに対する考え方など、住居に対する考えは本当に様々なので、
「これが共通の正解」というのは、ないと思います。
このため、本記事は、あくまで参考程度にご覧いただけたらと思います。
それでは本題に行きましょう。
以下に、私達がマイホームを購入した理由・メリットを記載します。
- 職場から家賃補助が出ない
- 老後は家を借りにくい
- ローン返済後は資産として残る
大きく、この3点ですね。
まず1つ目。私たち夫婦は、職場からの家賃補助がありませんでした。
これはかなり大きかったですね。
友人の会社は全国転勤ありというのもあって、10万円以上の補助があるそうです。
はっきり言って、ここまで補助が出るなら賃貸暮らしにして、
余ったお金を投資に回す生活を選択しますね。
私達は家賃補助0円ですので、家賃はドブに捨てるようなものです。

これが本当に悔しくて、マイホーム購入の1番の理由かもしれません。
2つ目は、老後のことです。

職がなくなると、賃貸を申し込んでも、大家さんから許可が出ない事があるそうです。
実際私達もアパートを持ってみて、大家さんの気持ちがわかります。
職業に就いていても、年収が低いと、家賃滞納を心配してしまいますから。
あと、高齢だと賃貸中に死亡するリスクもありますよね。
全く住める所がないというわけではないでしょうが、
選べる住まいは、確実に限定されてしまいますね。
3つ目の理由は、ローン返済後は資産になるという点です。
ローン返済後もそのまま住めば、住居費は無くなります。
また、ファミリー向け賃貸として活用し、自分達夫婦は田舎暮らしも可能です。
もしくは売却すれば、それまで返済してきた元金の一部が現金一括で手元に残ります。
元金返済の一部は、貯金という機能を持ちます。
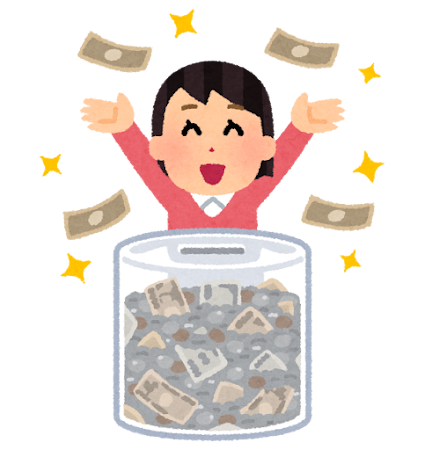
ローン返済後に様々な選択肢ができる点は、マイホームのメリットと考えます。
そのためにも、資産価値が残りやすい物件を購入することが重要になりますね。
今後、全国的に人口は減少していきますが、都市は人口が集中すると考えています。
特に東京は中央省庁や大企業の本社が数多くありますので、
実需・賃貸共に需要は落ちにくいと思います。
また、最近はマイカーを持つ人も少ないので、鉄道駅の近くは価値が落ちにくいでしょう。
我が家は、23区内の駅徒歩5分以内で平坦という条件で物件を探しました。
繰り返しになりますが、住居については様々な考え方がありますね。
時間重視で職住近接型なら賃貸で柔軟にした方が良いですし、
子育て重視で教育機関の整った地域に住むといった考えもあります。
賃貸暮らしにするか、マイホームを購入するかを考える前に、
まず、自分達がどのような人生を送りたいかを明確にすることをお勧めします。
次回は、マイホーム購入までの軌跡をお届けいたします。
お楽しみに☆彡



コメント